投資を始めるなら、まず悩むのが「どの証券会社を使うか?」ということ。
僕も最初は楽天証券やSBI証券、さらには銀行系証券まで比較検討しました。
その中で僕が選んだのは「SBI証券」です。
理由は明確で、「手数料が安くて、クレカ積立でポイントがもらえる」から。
この記事では、僕が実際にSBI証券を使って感じたメリットや、他社との比較、初心者にもおすすめできる理由を解説していきます。
僕がSBI証券を選んだ理由
投資を始めるにあたって、最初に悩んだのが「どの証券会社を使うか?」ということでした。
当時の僕は完全な初心者。右も左も分からない中、いろいろ調べていく中で、
SBI証券が他の証券会社と比べて非常に優れていると感じたんです。
特に僕がSBI証券を選んだのには、以下の3つの理由があります。
① 業界トップクラスの低コスト(手数料)
まず何より大きかったのが、投資信託の購入手数料が無料(ノーロード)であること。
たとえば銀行で投資信託を購入しようとすると、平気で2〜3%の購入手数料がかかることもあります。
長期投資を前提とするなら、この手数料差はとてつもなく大きな差になります。
SBI証券なら、人気のインデックスファンド(たとえば「eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)」)も手数料0円で買付できるので、コストを気にせず安心して始められました。
② クレジットカード積立でポイント還元がある
もう一つ決め手になったのが、クレジットカードで積立投資をするとポイントが貯まることです。
SBI証券では「三井住友カード」と連携することで、
最大で月5万円までの積立額に対して1.0%のVポイント還元が受けられます(カード種別による)。
年間で考えると、例えば月5万円の積立なら、6,000円分のポイントがタダでもらえるわけです。
実質的な利回りが0.5〜1%上乗せされるようなものなので、これを見逃す手はありません。
ポイントは日常の買い物にも使えるので、現金還元と同じくらいのありがたさがあります。
③ 自分には「楽天経済圏」の恩恵が少なかった
実は、当初は楽天証券と迷っていました。
楽天カードによるクレカ積立で同様にポイント還元がありますし、
楽天経済圏と組み合わせればお得になることも多いです。
でも僕の場合、楽天市場も楽天モバイルも使っておらず、
いわゆる楽天経済圏にどっぷりというライフスタイルではありませんでした。
そうなると、楽天経済圏の恩恵を最大限に受けることができない。
一方でSBI証券なら、「楽天圏」でなくても十分にお得で、
誰にとっても平等に低コスト&高機能。この点が、自分には非常にフィットしました。
銀行や他の証券会社を選ばなかった理由
証券会社を選ぶ際には、銀行窓口や他のネット証券も候補として検討しました。
でも、最終的にそれらを選ばなかったのには明確な理由があります。
① 銀行は手数料が高すぎて論外だった
まず最初に「なんとなく安心感があるから」と、地元の銀行の窓口を覗いたことがあります。
でも出てきた提案は、手数料が2~3%もかかるアクティブファンドばかり。
しかも、説明を聞いてもどんな内容なのかはっきり分からず、
担当者の言うままに契約しそうな雰囲気…。
「これはカモられるな」と直感しました。
長期投資において、手数料は資産形成のスピードを大きく左右する重要な要素です。
投資先の中身よりも、まずコストがどうなっているかを見るクセをつけるのが大事だと気付き、
銀行は候補から即除外しました。
店舗型証券会社は営業色が強くて不安
次に考えたのが、いわゆる大手証券会社(野村證券、大和証券など)です。
これらは昔からある「王道」のイメージがあったのですが、
調べていくとやはり営業成績を重視した売り込み型のスタイルが色濃く残っているようでした。
初心者が言われるがまま商品を買わされ、気づけば手数料まみれ…という話も耳にし、
「ここは僕のような凡人が入る場所じゃない」と判断しました。
③ 他のネット証券も検討したけど、SBIの利便性と還元率が上だった
ネット証券に絞ったあとは、楽天証券やマネックス証券、auカブコム証券なども一通り比較しました。
・楽天証券:楽天経済圏に強いが、改悪が続いていてやや不安
・マネックス証券:iDeCoに強いけどクレカ積立の還元率はやや低め
・auカブコム証券:三菱UFJ系で安心感はあるが、使い勝手で劣る
それに対してSBI証券は、サービスのバランスが非常によく、今後の拡張性もあると感じました。
特にクレカ積立+ポイント還元+TポイントやVポイントを使った投信購入など、
他社にない柔軟性と還元の選択肢が魅力的でした。
SBI証券のおすすめポイントまとめ(初心者向け)
僕がSBI証券を選んだのは偶然ではなく、
調べていく中で「結局ここが最強じゃないか?」という結論にたどり着いたからです。
特に初心者にこそおすすめしたい理由を以下にまとめます。
① クレカ積立でポイント還元が受けられる
SBI証券では、三井住友カードを使って投資信託を積み立てると、最大で5%(※プラチナカード)のポイント還元が受けられます。
通常の「三井住友カード(NL)」でも0.5%の還元があるので、銀行に預けるよりよっぽどお得です。
もらったVポイントはそのまま投資に使えるのも大きなメリット。まさに「ポイントで資産形成」が可能です。
② 投資信託のラインナップが豊富で迷わない
「選べるファンドが多すぎて迷いそう」と思うかもしれませんが、
実際には優良なインデックスファンドが検索しやすく、ランキングや比較機能も使いやすいです。
僕のように「オルカン一本でいい」というシンプル派でも、迷わず必要な商品にたどり着けます。
③ 新NISAに完全対応、長期投資に最適
2024年から始まった新NISA制度にもSBI証券は完全対応。
つみたて投資枠と成長投資枠の両方に対応しており、
制度スタート当初からスムーズに使えるUIや解説ページも充実しています。
僕自身も新NISAを使って毎月35万円を積み立てており、SBIの使いやすさを実感しています。
④ 口座開設から取引までがスムーズ
手続きが煩雑だと最初の一歩が億劫になりがちですが、
SBI証券はマイナンバーを使えばスマホで数分で申し込み完了。
数日後には取引も開始できるため、思い立ったらすぐに始められるのもポイントです。
⑤ 手数料がとにかく安い(というか無料)
SBI証券では、多くのインデックスファンドの買付手数料が無料です。
また、新NISAに対応した投資信託やETFも手数料無料の商品が揃っており、
長期的な資産形成に最適な環境が整っています。
SBI証券を始めるなら今がチャンス!
僕がSBI証券で投資を始めたのは、資産形成を本気で考え始めたタイミングでした。
最初はよくわからずに始めた部分もありましたが、
「もっと早く始めればよかった」と今では本気で思っています。
新NISA開始で「非課税枠の活用」が必須になった
2024年から新NISAがスタートし、生涯投資枠1,800万円までの利益が非課税になるという大きなチャンスが訪れました。
特に僕のように「FIRE(早期リタイア)」を目指している人にとっては、この非課税枠をいかに早く埋めていくかが重要です。
そして、その環境が整っているのがSBI証券でした。
ポイント還元+ノーロード商品で「堅実に資産を増やせる」
クレカ積立でポイントが貯まり、手数料も無料(ノーロード)。
運用コストを抑えながらコツコツ積み立てていけるのは、長期投資の王道です。
実際、僕も2022年から投資信託を積み立ててきた結果、含み益が500万円以上出ている状況です。
もちろん運にも左右されますが、「長く続けることが一番のリスクヘッジ」であることを日々感じています。
SBI証券は「始めやすく、続けやすい」
資を始めるにあたって不安はつきものですが、
SBI証券は操作性もよく、サポートも丁寧。
「初心者でも安心して使える」という点は、実際に使ってきた僕自身が保証します。
今の環境で一番おすすめできる証券会社はどこか?
と聞かれたら、迷わず「SBI証券」と答えます。
まとめ|SBI証券は、長期投資を始めたい人の最適解
SBI証券を使い続けてきた僕が思うのは、「とにかく投資がしやすい」ということ。
手数料の安さ、クレカ積立によるポイント還元、豊富な取扱商品といった利点は、
他の証券会社と比較しても頭ひとつ抜けています。
楽天証券やマネックス証券も候補には挙がるかもしれませんが、
楽天経済圏に依存しない僕のようなタイプにとっては、SBI証券一択でした。
これから投資を始める方や、つみたて投資を継続していきたい方にとって、
SBI証券はとても頼もしいパートナーになるはずです。
実際にSBI証券で数年にわたって積立投資を続け、資産も着実に増やせています。
これから投資を始めるなら、僕と同じように**「まずSBI証券を使ってみる」**ことをおすすめします。

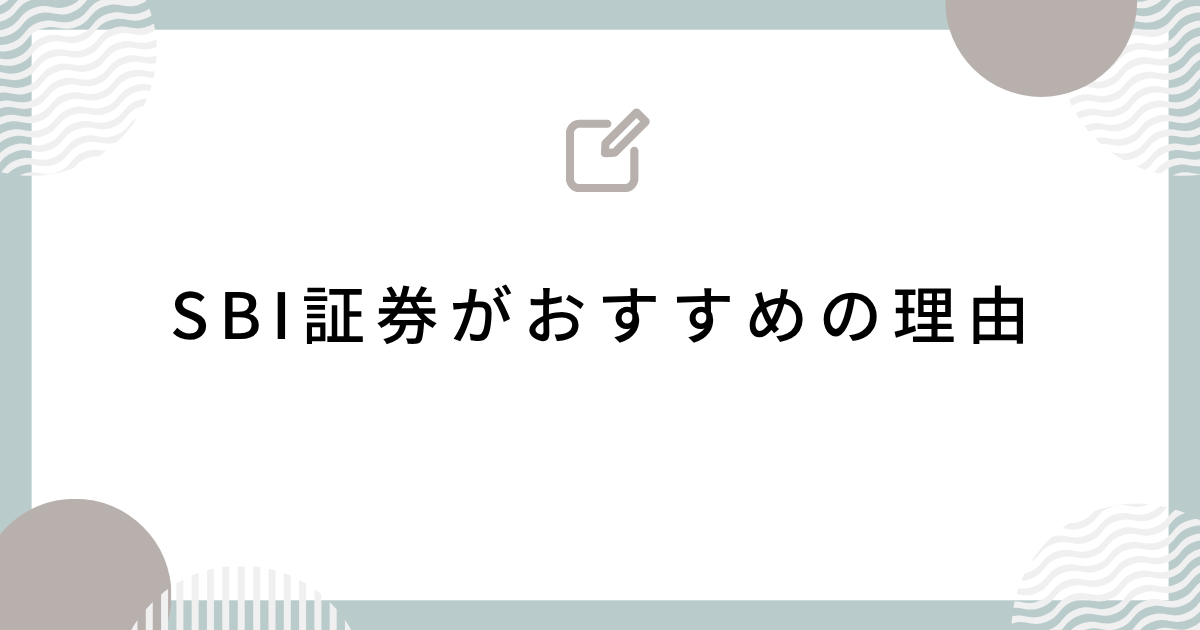
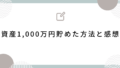
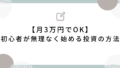
コメント